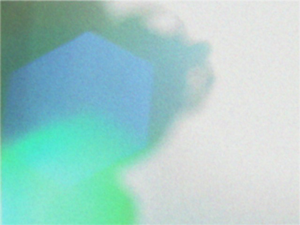![]() ALA-SCOPE 02「映像レーベル・ソルコードの作家たち」
ALA-SCOPE 02「映像レーベル・ソルコードの作家たち」
1 齋藤正和 SAITO Masakazu
あいちトリエンナーレ2016による、現代の表現や各地のアートシーンに迫るイベントシリーズ「ALA-SCOPE」にて、SOL CHORDの作家作品の上映イベントを4回に渡り開催しました。この上映イベントでは松井茂氏(詩人)が聞き手となり、作者が自作について語ります。
第1回目はsc-010『休日映画 2009 - 2014』の齋藤正和さんの作品を上映しました。この時のトークの模様を書き起こしでお届けします。
2016年6月18日(土) 19時開場 / 19時30分上映スタート
トークゲスト:松井茂(詩人、情報科学芸術大学院大学准教授)
あなたにとって映像とはなんですか?

松井: よろしくお願いします。トークゲストと書いてありますが、4回全部に出るので、ゲストはどっちなんだろうかと思っています(笑)。換言すれば、「映像レーベル・ソルコードの作家たち」というタイトルで、インタビュアーを固定して行うことで、レーベルの性格と共に、現在の映像のあり方を見せていく、議論していこうという試みだと思っています。
で、早速ですが、本日拝見した4作品は『A Piece of Sunsession #02』(2001)、『動の影 岩下徹というからだ』(2008)、『たまたび 春水荘 2012』(2012)、『常滑アーカイブ#01 下村進』(2013)でした。僕は、レーベルから発売されているDVD『休日映画』(2015)は拝見しているのですが、これには、『A Piece of Sunsession #02』のフルバージョンが収録されています。つまり、それ以外の3作品は初見でした。DVDのタイトルにもなっている『休日映画』(2014)の印象で足を運んだので、今日のプログラムは、僕が想定していた齋藤さんと、随分趣向が違いまして、気持ちよく期待を裏切っていただきました。本日は、この点をいろいろ伺っていきたい。他方で『休日映画』にも関わりますが、今日のプログラムは、映像メディアの属性としてという以上に、より積極的な表現として、記録がテーマになっていたと思います。2001年の段階で果たして記録という意識がどれくらいあったのかはさておきですが、議論のとっかかりとして、いきなり大きな話ですが、齋藤さんにとって「映像とは何か?」という無茶振りをしたいと思います。今日の4作品は手法が異なる記録の諸相であるわけですが、それはそれで伺いますが、まずは齋藤さんが考える映像とはどういうものと考えていらっしゃいますか?
齋藤: おっしゃっていただいた記録性、実写映像が持つ特性、写真的に言えば、「それはかつてあった」的な、インデックス性には興味があります。アニメーションも制作したことがあるのですが、その場合もロトスコープという手法で、要するに「物体がある現実世界、その痕跡としての映像」の写しです。実写映像だったり、アニメーションだったり、インスタレーションだったりと手法・形態が変わろうと、「自分で撮影した映像素材」をベースにして作品を制作しています。
映像表現とメディア環境の変化
松井: 『A Piece of Sunsession #02』ですが、コンピュータ自動編集による映像作品と書かれていますが、具体的にどういうことをしている、あるいはさせているのでしょうか? 同時に思うこととしては、自動なら映像はなんでもいいのではないか?という気もします。意地の悪い質問で恐縮ですが、自動生成として編集を放棄するのであれば、そこで扱われる映像はなんでもいいことになりはしないか? 実際には、敢えてだと思いますが、すごいプライベートな映像素材を扱っていますよね。
齋藤: はい。自動編集は、Maxというプログラムを使用して自分で組んでいます。長い素材の映像をつまんで、2秒使って40秒捨ててまた2秒使って40秒捨ててみたいなことをやらせています。ただ、この捨てた40秒の間の時間の流れが損なわれるので、そこを短くパパパッと3フレームくらい表示し、それによって間を繋ぐということをやっています。 そもそも自動編集することで自分が意図しない素材に出会えるというところに興味がありました。そうなってくると素材は何でもいいということになるのではないかという指摘ですが、この作品の映像素材は、沖縄に行って、しかも沖縄の何かの問題を扱うのではなくて、旅行者の目線というか、オリエンタリズムというか、いわゆる一般的な“沖縄”を撮っているわけです。そういうプライベートな映像素材を自分が編集してしまうと、自分が好きなものだけが並んでなんともならないのではいかと。いわゆるホーム・ムービーみたいなものになってしまう、という問題意識がありました。その時に、自動編集を用いることで映像に対してある距離感を出すことが出来るのではないかと思いました。要するにプライベートな眼差しで撮ったものだからこそ、自動編集がはまるのではないかと。それは作品の前半で動画を静止画にしていたことにも関連します。静止画にすることで動画と違った距離感が生まれることを意識し、前半パートは静止画で、後半は動画になっていく構成を組みました。
松井: 僕が1975年生まれで、齋藤さんが1976年生まれで、映像を撮る技術に関していうと、90年代はビデオ・テープだったり、まだフィルムもある程度使えるところから始まる。そうこうしているうちに、デジタルの撮影機器が登場するといった、メディア環境が激変する時期に制作を始めた世代にあたると思うんですが、技術的な関心が、すごく高まった時期として、90年代後半からゼロ年代があった気がします。
齋藤: まさに、映像においてはカメラがデジタル化し、コンピュータで手軽に編集ができるようになったという時で、今までと違う映像の扱い方の可能性が拡がりましたね。例えばHD(ハイディフィニション・フォーマット)が出てきたとき、それで何ができるのかという考え方。メディア環境といいますか、それだけだと単なる技術検証みたいなことになるのですが、そういうものと「撮るもの」を同時に考えていくことが、ずっとありました。コンピュータに関していえば2000年前後は確かに大きな節目だったので、そこを扱っていこうという意識はあったように思います。
松井: 流行りは過ぎたかもしれないけれども、ある種ポスト・ヒューマン的な映像作品のあり方、実際に自分で撮っているんだけれども、非常に暴力的な編集がなされているというか──いまだったらビックデータとかそういう形での、新しいAIが編集するとかいう可能性もあると思うんですけど──、2000年当時のデジタル・ヒュマニティーズ的な暴力による編集が、プライベートな映像をざっくざっくにするという、僕はいま見てもこの当時の技術的な暴力性は、未だ新鮮な迫力を感じます。メディア環境の変化が要請する初期衝動でしょうか、単に趣味かもしれませんけど、アルゴリズム的な処理の可能性が表現として感じられた。「感じられた」と過去形で言いましたが、「感じられた」という手応えによって、アルゴリズム的な方法論が確立された時期だったことを想起しました。
撮影が誘発する身体の記録
松井: さて、こうしたポスト・ヒューマンな手法を手にして、もっと破局的な記録の変形に突っ走るかと思いきや、2008年の『動の影 岩下徹というからだ』では、眼前のフィジカルを正確にトレースしてみせますね。もちろん正確にというのは、単に撮るわけではなくて、細部の残像効果を強調することによって、不可視なレベルでの映像表現によって、新しい正確さを追求したとでもいう感じですね。この作品の制作の動機と、どんなメディア環境で撮影されたのかを伺えますか?
齋藤: コンピュータによる編集は2005、6年くらいまでやっていたのですけれども、自分の生活環境が変わったタイミング、働きだしたことで常にカメラを持っているわけにもいかなくなって日常的なスナップが撮りにくくなった時に、自動編集から一度離れてみようと思いました。ちょうど2006年頃に、やっとHD(ハイディフィニション・フォーマット)で制作できる環境になってきたということがあり、その時の興味としては「ブレ・ボケに対する鮮明な画像」といったことに加えて「インスタレーションにした時にも画質が保てる」ということがありました。元々、これはインスタレーション作品でして、映像インスタレーションに興味が段々と移っていく時期の作品です。実際、どのように撮影しているかといいますと、真ん中に踊っている方がいて左右にそれがボケた映像があるシーンを例にしますと、実際に収録する時には、ダンサーの方にそのボケた映像(自身の動きの軌跡)をリアルタイムで見ていただいています。つまり、「自分自身とダンスを踊る」といった環境を用意したわけです。というのは、岩下さんは即興で踊られる方で、何か周りの状況に対して動きを紡いでいくという踊り方をされる人なので、その環境としてそういうものを用意して撮影を試みました。
松井: つまり岩下さんはモニタを見ながら、それにリアクションしているということなんですね。通常だったら鏡を見ながらリアルタイムに──鏡がリアルタイムというのもなんですが、鏡は最も正確なカメラでモニタですけど──、ということに対して、むしろ映像がちょっとディレイする、つまり、自身の一瞬前の痕跡を見て、ディレイの中で身体を作っていくということなんですね。
齋藤: そうですね。次の動きを自身に決められるみたいなことをやってみたいと思っていました。
松井: 齋藤さんの撮影のセットが、記録のためとはいえ、舞台装置みたいな機能を岩下さんに及ぼしていたということですね。
齋藤: はい、そのようなことを意図していました。
松井: 『A Piece of Sunsession #02』は編集点を自動に任せて、ざっくざっくにしているのに対して、『動の影 岩下徹というからだ』は、肉眼では見えない軌跡までもなめらかに強調して、むしろ接続していく編集に見えるのが面白いですね。
齋藤: 編集においては素直につないでいます。岩下さんの言葉、自身がどのように活動されてきたかを伝えていくことをベースに、映像をはめていったという形になりますね。
松井: このときには、岩下さんの記録を撮ろうという意図はかなり意識的でしたか?
齋藤: ビデオ・ポートレートをやりたいとは思っていました。それと同時に動きの可視化への興味がありました。
松井: 映像の特性だと思うんですが、ドラマでもドキュメンタリーでも、経年劣化する人間の記録になるというのは宿命ですよね。僕は、そこになにか記録性としかいえない焦点があるような気がしているのですが、そんなあたりのことを意図されたことはありますか?
齋藤: その頃は、まだ記録というより動きをどう可視化できるかということに比重がよっていました。これを今後見るだろうとか、この時点で残しておかなければというような意識は薄かったです。ただ、声をお聞きして、映像、ビジュアル、ダンスといったものよりも、この声を残したいというか、特徴的だなと感じました。実は、この作品以後「声もの・ナレーションもの」に展開していく流れがあります。
場所固有の時間を記録する
松井: 後半の作品『たまたび -春水荘2012 -』と『常滑アーカイブ#01〜下村進〜』は、コミッションワークということになるのでしょうか?
齋藤: そうですね。お題というか、ここをおさえなきければみたいなものがあって、じゃあ自分なりにどうアプローチするかという感じですね。
松井: 『たまたび -春水荘2012 -』は、ビデオ・インスタレーション作品と書いてありますけど、本来はスクリーニングの作品ではなかったわけですか?
齋藤: はい、違います。映像の中に風船がたくさん跳ねていた宴会場が出ていましたけれども、オリジナルは、あそこに2メートルくらいの巨大な風船を設置しまして、そこに今日観て頂いた映像の一部を投影した作品でした。「撮影された場所で、その場所の映像を見る」という体験をベースに、真っ暗な中で映像だけを見るというよりは、上映が行われているその場も観てもらいたいという意図がありました。なので、映像の中でライトが光ると会場にあるライトが映像と同期して光るといった、空間にも目がいくような仕掛けを導入しています。今回上映したものは、そこで使用した映像を再編集したものです。
松井: 作品の中では、風船が動線を誘導していくというか、ナレーションのおばあさんと同期してストーリーテラーみたいなキャラクターになっているけれど、あの風船にプロジェクションしているという見せ方だったわけですね。
岩下さんの作品の流れに接続すると、『たまたび -春水荘2012 -』でも声に着目してますね。おばあさんの語り。
齋藤: そうですね。「春水荘」で面白いのは建物だったので、必ずしもおばあさん自体の表象が写っている必要はないと考えました。ただ、建物に関する来歴は必要だと思っていて、それをナレーションやテロップで出すのも違って、声が持っている肉感というか、それに興味があるというか、必要だなと思っていました。
松井: 今日はこの会場におばあさんは来てないですよね、まさかね。僕の勘違いだったらごめんなさいね。僕、風船がいっぱい浮かんでいる部屋と声が重なったときに、ああ、このおばあさん死んじゃっているんだと(笑)なんか霊がただよっている場所として、そういう方向に頭が向いたというか、物語的に解読して、脚本があるような、演出のようにも思っちゃいましたが、リサーチを重ねながら、建物のどういう部分を撮っていくかとか、どういう話をヴォイスオーバーしていくのかという設計がなされたわけですよね?
齋藤: 温泉街自体もさびれているので、10年後とかにはおそらくこの建物自体もないだろうという思いがありました。なので、「春水荘」の特徴的な場所を撮っておきたいというのがあって… そして、おばあさんの話を聞いて、それを何とか時間軸上におさめていく。もう一つの軸は、風船をお客さんに見立てて、お客さんが館内をさまよって一泊して、夜が明けて、出発するといった、そういう緩やかな時間の流れがあれば、15分構成できるのではないかと思いました。
松井: おばあさんが先だったんですか?
齋藤: どちらとも言えないところがあります。場所が強すぎて、ここを扱うと何をしても負けちゃうように思って、最初は「春水荘」を扱うことを躊躇していました。ただ、このおばあさんとしゃべってみて、その声に可能性を感じました。そのうえで、やっぱりこの建物はいずれ無くなるだろうという思いもあって、10年後くらいに見ることを想定しながら作ろうと思いました。なので、ニュース映像、新聞も入れていこうと。
松井: 『たまたび -春水荘2012 -』では、沖縄でのオスプレイのニュースが流れますよね。時期が特定できるというか、先ほど指摘した経年劣化というか、撮影された時間と、上映される現在の距離をはかる指標みたいにも見えますよね。

複雑化する編集点への指向
松井: このシーンにも関連するのですが、齋藤作品の特徴として、僕が注目したいのは、映されているものと音のズレなんです。映像におけるサウンドデザインって、同期か非同期しかないと思うんです、ちょっと暴論ですけど。とりあえずそれを許容して話すと、齋藤さんは徹底して非同期させている。『休日映画』も実は、撮ったときの画と、同時録音された音が対応するシーンは皆無ですよね。
齋藤: そうですね。
松井: 音と映像のズレというのが、映像の編集点とまた違う所で、音の編集点を作っているような気がして、この輻輳する編集点が単なる映像の属性としての記録を逸脱した、表現としての記録を見出す契機になっていると思うんです。
齋藤: 非同期の方が構成しやすいのはありますね。先に音を出して画が後から来るとか、時間的な前後ができるというのもありますし。ただ、今日の作品でいうと『A Piece of Sunsession #02』は全く同期しているんですけれども。
松井: でも映像は切れちゃうから非同期になりますよね。
齋藤: ああ、なるほど。そうですね。
でも、何となく、特に声を扱い出してからは、非同期の方が組みやすいというのはありますね。要するに「自分の眼差しを記録する」といった所から離れた瞬間に、そういうコンポジションへの自由度が自分の中で出たというか… 以前はいかに自分が見ているものを写し込むか、音も含めて、といったところでアプローチしていたのですけれども、そういうところから離れた作風になってきて、コンポジションの可能性が出てきたのかなあという感じでしょうか。
松井: 『A Piece of Sunsession #02』は、クリス・マルケルの『ラ・ジュテ』(1962)を想起しますよね。動画で全編とったにも関わらず、それを静止画だけで構成した作品ですが、齋藤さんの作品は、現在のメディア環境からそういった映画史における実験の手法への批評として、デジタルという視座からの発言にもとれますよね。齋藤さん自身の意識、無意識を超えて、メディア技術の経年劣化に対して、メディア技術で更新し、それでも問われるべき映像の特性を追求した結果として現れる、ある種のアヴァンギャルドな方法論と言う感じ。アヴァンギャルドって言うと、なにかすごく過剰でヘンなことを想起されるかもしれませんが、齋藤作品は過剰に見せないナチュラリズムも感じられるところが、なんか興味深い。勝手な印象ですが、これって、ソルコードの作家たちの特徴かもしれないですね。
映像作品のプロトコルはどこにあるか
松井: 本日最後に上映された『常滑アーカイブ#01〜下村進〜』これはシリーズですね。ご自身では、どんな試みと位置づけられていますか?
齋藤: 岩下さんとの仕事以降、自分の眼差しというよりは、取材したもの・人を残していくことに興味が出てきました。個人的なものは『休日映画』の方でやっていて、それとは別のプロジェクトとして自分の中で走らせているように意識しています。『たまたび -春水荘2012 -』は僕が撮影と編集を担当していましたが、『常滑アーカイブ#01〜下村進〜』に関しては、もう少し自分の手から離れているというか、アニメーション部分は学生に任せていまして、撮影も一部は学生が担当したり、より編集だけに関わるようになっていきました。その後も『常滑アーカイブ#02、#03』とありますが、一人で作るのではなくて、どんどん自分の手から離れていっているという感じですね。監修みたいな立ち位置になってきました。
松井: クレジットで編集は捨ててないですね。
齋藤: そうですね、編集がまだ離れてない。離すべきなのかもちょっとわかんないですけれども。
松井: コンピュータの自動編集も設定するのは自分ですから、それも編集行為だというふうに含めれば、編集を捨てたことは一度も無く、やはりむしろ編集には偏執的にこだわっているようにも見えますよね。撮影に全く参加していないような場合でも、自分が編集するということによって、自分の映像作品は成立するとも考えられますか?
齋藤: そうですね。タルコフスキーか誰かが、編集を見ればそれが誰の監督した作品かわかるみたいなことを言っていたのですけれども、編集にこそ個人の特性というか作家性が表れるのかなというのはあります。だから、劇映画の編集とかはまた違うとは思うのですが、ある素材をぽんと渡されて、それをどう編集するかということで作家性を垣間見せるということも十分考えられると思います。
『休日映画』の可能性を考える
松井: 記録と撮影ということの関係性というか、そこに映像表現の問題をどのように考えていけばいいのかということが、素朴に困難になっている気がしています。凡庸な発言をすると、近年あらゆる状況が、記録として撮影されている、監視カメラはもちろんのこと、PCもネットワーク越しに監視しているとか言われますし、むしろ記録されていない瞬間なんてないというか、記録されていないシーンは存在しないというようにさえ感じられます。そう考えると、映像は特権的な技術によって撮影されるものではなく、むしろ映像という環境こそが日常になっている。比喩ではなくて、映像こそが日常になっている。そう捉え返すと「記録とは何か?」という問題が、映像作家に突きつけられるのではないかと思います。同時に、そこに踏み込んで表現と接続することはどのように可能と考えられるのか? そのあたりについて、どうでしょう?
齋藤: 記録にこだわるのであれば、さっきの旅館も淡々と全部、それこそ、ストリートビューみたいなもので、オールオーバーに撮るという方法もあるでしょう。淡々と隅々まで撮っていけばいいのですけれども、多分、それを見ようと思わない。もちろん記録性、資料としての価値はあるでしょうけれども、それを見ようと思えないのではないかと。そこでここ最近考えているのは、やっぱり物語ですね。ずっと避けてきたというか、自分が出来ない分野だったので扱えていなかったわけですけれども、物語といっても、さっきの「風船が一泊して帰る」みたいな、それくらいの緩やかな時間の流れを与えることによって、資料価値の部分と、表現として見れるものを同時成立させていきたいなというのが最近の、自分の中の意識です。
松井: とはいえ、撮影という作家の行為が失権しつつあるときに、作家はなにをする、できるのだろうか? みたいな状況をどう考えるのか、その辺て、なんかいま極まっちゃってる気がしませんか?
齋藤: おっしゃる通り確かに、撮ること自体には。
松井: 他方で、編集の専門性も、アプリケーションに依存してしまうと、なんだかプレーンな物になってしまうのでは無いかと思ったりします。また、絵画表現は、絵の具の歴史とか、メディア固有の目的と技術の発展が一致してますが、映像表現というのは、表現のために技術というのは、なかなか発達しませんよね。民生品だし、アプリケーションだって同じです。独自に開発するということはあるかもしれませんけど。私がそんなこと思い詰める必要は無いんだけど、そういう意味で、行き詰まっている感じを憶えるときがあって、そういう意味で『休日映画』は、毎回、撮り方と編集点を重ねた実験を繰り返している個人の力というか、家族の力が、すごく新鮮で力強いですよね。「こういう可能性もあるのか!」みたいな清々しさを感じます。
齋藤: なるほど。確かに、『休日映画』は毎回短い中で、一つの、何か実験をしようというのはありまして、それは機材だったり撮り方だったり、おっしゃって頂いたように編集だったりもします。結局、編集も「語り口」なのかもしれないですけど、結局そこにいくのかなと。
松井: それは先程おっしゃっていた物語っていうことですか?
齋藤: はい。結局そこなのかなっていうのが薄々あるんですけど、その一方で技術・編集方法含めあらゆることをリサーチしておきたいというか、自分で実験しておきたいっていうのが『休日映画』です。物語以外の可能性は、それはそれで同時に常に探りたいなとは思っています。その可能性が具体的に何だっていうのはまだ無いですけど。
質疑応答

司会: 何か今日の感想なりご質問なりある方はぜひ挙手をお願いします。
客: 今日はありがとうございました。最初に上映された『A Piece of Sunsession #02』に関して質問があるのですが、先程、自動編集はMAXを使って尺をランダムに選んでいくというのを聞いたのですが音声の尺はどのようにやられていたのでしょうか。
齋藤: 音声も映像と一緒にやっています。
客: でも映像が細切れのときに、音声だけは正常に流れている部分が結構あったと思うんですけど、あれは狙ってやったのでしょうか。
齋藤: そうですね、ある5秒なら5秒の1秒目2秒目3秒目の映像の最初のフレームだけ見せるみたいなことをやっていまして、尺のとりかたとしては同期しています。再生されれば映像と音はあっていて、その1フレームをとめているので、ちょっと非同期に見えるという状態です。
客: ありがとうございます。個人的な感想ですけど、それですごい想像の余地があるというか、静止画だけを見ながら音声を聞くことによって、なんかわかんないんだけど、こうかなっていうのが色々想像できてすごく良かったです。
齋藤: ありがとうございます。
松井: ドゥルーズの『シネマ』でスローモーションの話が出てきますけれども──勘違いだったらごめんなさい──、その流れで誰かと話した際に、映像はスローモーションにしても音はスローモーションにならない。映像は静止してももちろんイメージが見えるわけだけれど、音は静止するとなにも聞こえなくなってしまうというようなことが話題になりました。これは技術の問題なのか、現象として自明の問題なのか、僕にはわかりませんが、今日は、齋藤さんの作品を通じて、映像メディアの根源的な問題を、捉え直す機会になった気がして、とっても面白かったです。
最後に、同時代に生きている作家を見る楽しみというのは、100年とか経つとその作家の主要な作品しか残らないんですけど、どれが代表作になるのかまだ分からない形で、同じ社会状況の中で、作家の試行錯誤につきあえることだと思います。つまり、100年後には残らなくても、同時代に接する人間にとって重要な作品は別にあったりもするんです。それを見られ、一喜一憂できることが同時代を生きる醍醐味です。ぜひ、今日上映されたのと全く違う、全く違うと言っても、おんなじ作家が撮っているわけですから、扇子の要じゃないけれども重なっているわけで、とにかく皆さん『休日映画』を是非購入して観ていただきたいと思います。齋藤さん、本日はありがとうございました。
齋藤: ありがとうございます。
- - -
sc-010 『休日映画 2009 - 2014』齋藤 正和 Trailer
【ALA-SCOPE 02「映像レーベル・ソルコードの作家たち」】
主催:あいちトリエンナーレ実行委員会
共催:SOL CHORD
1 2016年6月18日(土)…齋藤正和
2 2016年7月22日(金)…池田泰教
3 2016年8月26日(金)…大木裕之
4 2016年9月16日(金)…前田真二郎
トークゲスト:松井茂(詩人)
時間:19時開場 19時30分上映開始(21時10分終了予定)
場所:アートラボあいち大津橋・2階
>>topに戻る