7 blinks after a decade
2021, 36‘02‘‘, Japan
01 “FATHER” MAEDA SHINJIRO
02 “WATARIDORI” NAKAZAWA AKI
03 “Small Sleep” SAITO MASAKAZU
04 “ITAMI” TAKASHI TOSHIKO
05 “IE” KIMURA NORIYUKI
06 “Ghosts” IKEDA YASUNORI
07 “KOUJITSU” HOMMA MURYO
上映情報|第68回オーバーハウゼン国際短編映画祭 インターナショナル オンライン コンペティション部門
2022.05.02 AM3:00(JST) International Online Competition 4
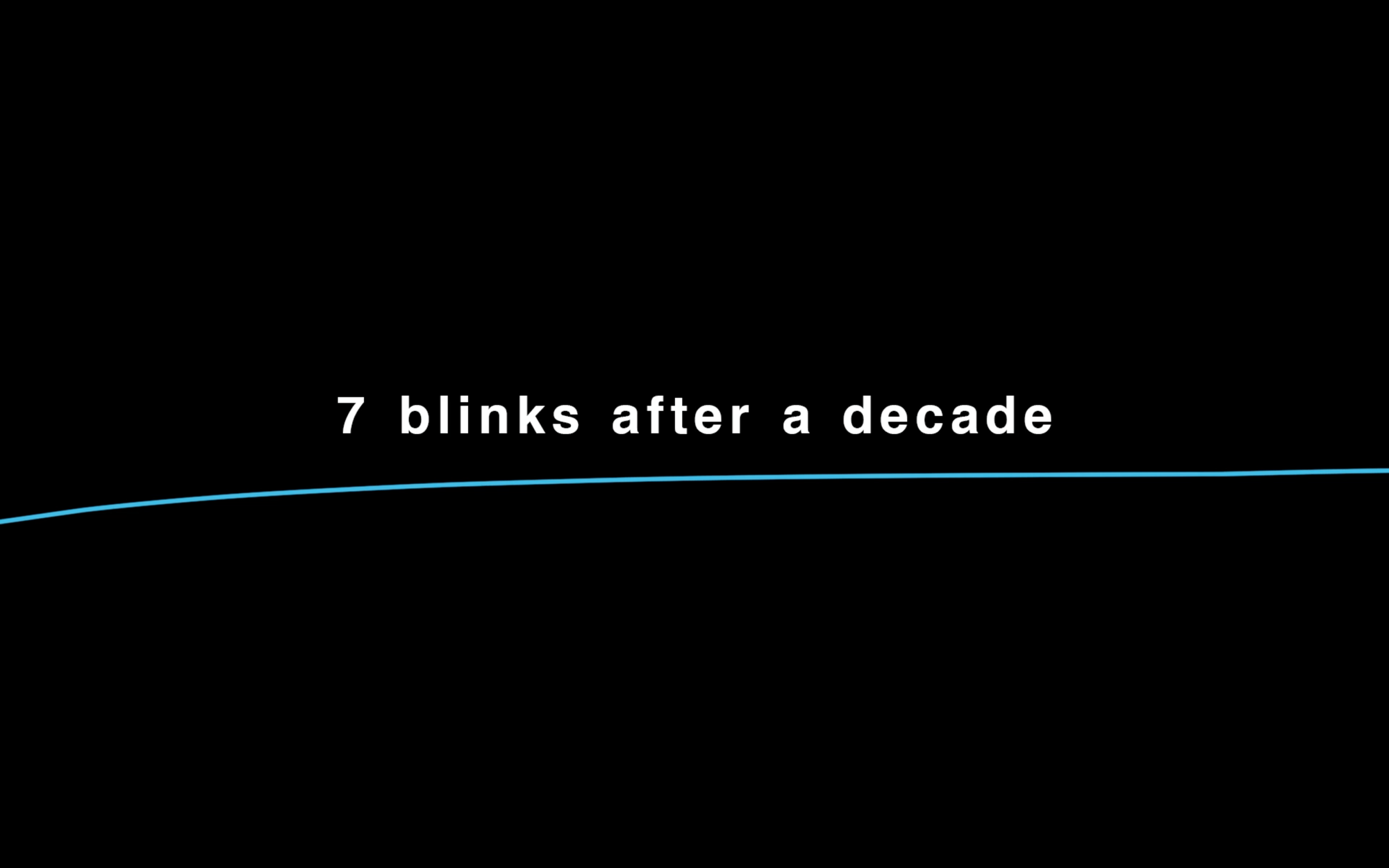







この映画は、津波と原発事故という大災害が日本を襲った2011年に立ち上げられたWEBムービー・プロジェクト「BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW(BYT)」が背景にあります。Covid19が世界中の人々の生活を脅かした2021年に再度制作された作品から7つを選んだオムニバス・ムービーです。10年前の状況と比較しながら、現在進行形の危機を提示します。
Short synopsis:
This film consists of 7 pieces that were initially produced for the online-movie-project "BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW (BYT)" launched in 2011 and reunited in 2021, when the big catastrophe of Tsunami and the nuclear powerplant accident hit Japan and the Corona-Pandemic threatened our life worldwide. The film presents the ongoing crisis mentioning and comparing the situation of ten years ago. >>English Page

前田真二郎
MAEDA SHINJIRO
この企画”BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW”の発起人。指示書のオリジナルは2008年に作成。2005年より映像レーベル”SOL CHORD”をオーガナイズ。舞台や美術など多領域のアーティストとの共同制作にも取り組む。
中沢あき
NAKAZAWA AKI
ケルン在住。キュレーター及び映像作家として様々な場と形で映像メディアに関わり、また在独の視点からコラムなども執筆する。「願いをひく/Drawing wishes」(2006)はベルリン国際映画祭、WRO’07 他世界各国の映画祭にて上映・受賞、またケルン市美術館収蔵品となる。
齋藤正和
SAITO MASAKAZU
実写映像の持つ記録性に着目しながら、シングル・チャンネルの作品やビデオ・インスタレーションを制作。主な作品に、コンピュータ自動編集による「Sunsession」シリーズや、家族をモチーフとした「休日映画」など。
崟利子
TAKASHI TOSHIKO
福田克彦監督の助監督、東京国際レズビアン&ゲイ映画祭のディレクター等を経て、映画制作を開始。代表作に『Blessed ―祝福―』(ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭特別賞)がある。近年は「伊丹シリーズ」を継続。
木村悟之
KIMURA NORIYUKI
自ら設定した規則に従って撮影を行う『軌跡映画』が代表作。2013年から2017年はドイツ(ケルン/デュッセルドルフ)で活動する。帰国後「21st DOMANI・明日展」(国立新美術館)に出品。現在、石川県を拠点に活動。
池田泰教
IKEDA YASUNORI
人物のポートレイトを映像で描く「3Portraits and JUNE NIGHT 」、49日間のドキュメンタリー作品「7×7」など撮影行為を起点にしたナラティブな表現を探求し、国内外で発表を続けている。
本間無量
MURYO HOMMA
フリーランスとして活動したのち、ライゾマティクス所属。テジタルビデオに関わる映像表現を主軸に幅広いフィールドで活動している。ELEVENPLAY x Rhizomatiks " S . P . A . C . E . "では撮影、編集を担当した。Curators' Statement
7 blinks after a decade
堀家敬嗣(映像研究・山口大学教授)
今世紀の最初の年、航空機に突入されて大都市の高層ビルが崩落していく映像を私たちは目撃した。2001年のアメリカ同時多発テロ事件は、しかし日本で暮らす私たちにとっていわば海の向こうの出来事だった。テレビ報道が伝えたその映像は確かに衝撃的であり、これに胸を痛めもしたが、それでも私たちの生活に緊迫した危機感をもたらすものではなかった。2011年に発生した東日本大震災は、多くの被害者を出した地震そのものに加え、これに起因する直接的または間接的な災害や災難が私たちの暮らしの安寧を揺さぶった。テレビ報道で繰り返し再生される映像は、自然による圧倒的な暴力への畏怖を私たちに再確認させたが、他方で人為的な無策がこの惨状をより難しいものとし、それゆえに私たちの生活や生命が右往左往したことも事実である。けれどなお、放射線量が次第に減衰していくように、この見えない脅威に対する危機感も震災の衝撃も、時間の推移にそって減少していった。あれからもう10年なのか、それともまだ10年なのか。長い瞬きののち、閉じた瞼を再び持ちあげられた瞳が対峙しているのは、新しい感染症の世界的な流行、そのパンデミックの光景である。この猛威は、幾度となく収束するかに思えてすでに2年近くの長きに渡り市民生活を混乱に陥れつづけ、社会は疲弊しつつある。2001年、2011年、2021年。映画のように突飛で荒唐無稽で悪夢的な、それゆえ日常の暮らしのなかではとても容易に受容し消化できない10年ごとの惨劇は、しかしいずれ時間の経過とともに他人ごとのように相対化されてしまう。本企画に参加した13名の映像作家が彼らなりの仕方で向きあったのは、こうした時間に対してである。うち7作品からこのエディションは編まれた。震災の記憶と感染症の猛威が交錯するなか、前田作品は、肉親の死を直視する。そこにあるのは、数値をとおして抽象化される匿名の死ではなく、かけがえのない存在の、交換不可能な、にもかかわらずけっして自分のものにはならない死である。震災の現場であれ感染症の現場であれ、現実の死とはそうしたものにほかならなかったはずだ。中沢作品は、ドイツから日本へと渡航する過程で感染症の猛威が社会に及ぼした深刻な影響とその恐怖に直面する。その猛威は、空間に人がいないこと、その不在性をもって視覚化される。つまりそれは、人の存在や営みが否定されることの恐怖なのである。10年前に撮影に訪れた場所を再来し、そのほとんど変容していない田舎の風景のなかで、子どもの成長や誕生といった変化が時間の経過と生活の歩みを印象づけるのが斎藤作品である。そこには、日々の暮らしにまぎれてたちどころに薄れてしまう記憶のために、この瞬間をじっくりみつめ、記録しようとするまなざしがある。崟作品もまた、10年前の反復を構想したものの、その実現を妨げたのは、感染症の猛威によって遠出はもちろん外出もままならない行動の制約である。崟は、この窮屈で不自由な制約を、緩やかなパンを含む唯一のショットの抑制的な長回しによって示唆しつつ、その空間から記憶を抽出していく。
元気のない犬に花粉症を疑うなどとりとめもない日常の会話は、日々の暮らしに対するメディア社会の並行性や虚構性を指摘し、その均質性を疑問視させるが、ただしここでもなお、幼稚園児は通園前の体温を計らなければならない。木村作品は、震災や感染症禍とおよそ無縁に見えて、むしろこれを日常としてともに生きていこうとする姿勢を提示する。もっとも演出性の濃厚な池田作品は、出演者である作家の家族が実際に震災を体験した被災地の家屋を舞台に、もはや誰も住まなくなったこの家でかつて暮らした家族を幽霊に見立てて震災当時を再現する。ストローブ=ユイレのように精緻で小津のように厳格なショットの組成においては、しかしむしろ家の側が幽霊なのであり、家族の身体はこれに音や声を貸す霊媒にすぎない。本間作品では、感染症禍の渋谷で時間が巻き戻され、誰もがわずかに後退りする。それでもやはり、なにもなかったことにはできない。なぜなら、彼らの誰もが、すでになにかが起きてしまったところからその後退りを開始しなければならないのだから。そしていま、彼らは、私たちは、再び長い瞬きをしようとしている。